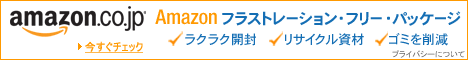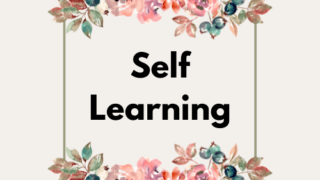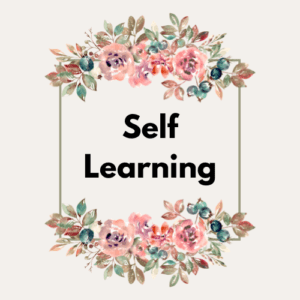これは大切!ワインをさらに美味しく飲む方法とテイスティングの基礎

ワインをさらに美味しく愉しむ上でいくつかポイントがあるのはご存じでしょうか。
簡単にお伝えしてしまうと適切なグラスの選択、注ぐ量、提供する温度、そしてスワリングについて、テイスティングにも触れながらお話していきます。これらの要素は、ワインの味わいや香りを最大限に引き出すために重要な役割を果たします。
適切なグラスの選択を
適切なグラスを選ぶことは、ワインの味わいを向上させるために欠かせません。ワインの特性に合ったグラスを選ぶことで、香り成分を適度な振動により拡散され、味わいが一層引き立ちます。
また、グラスの形状がワインの香りや味わいを変化させることがあります。
例えば赤ワイン用の大きめのボウル状グラスには香りを引き立て渋みを和らげるのに適しており、白ワイン用の小さめグラスにはフレッシュさや酸味を引き立てる効果があります。また、シャンパン用のフルートグラスは、炭酸ガスの持続性を高め華やかさと優雅さの場面も演出できます。
ワイングラスの形状は、グラスの中でワインの香りに集中できるように設計されています。ボウル型のグラスは香りの蒸発を抑え、香りをより集中させる効果があります。また、グラスのリム(口の部分)の形状も重要で、薄くカーブしていることでワインの流れをスムーズにし、口当たりの良さを引き出します。
注ぐ量に注意する
ワインを注ぐ量も重要な要素です。適切な量を注ぐことで、ワインが適切に空気に触れあい、香りや味わいがより引き出されます。
一般的には、グラスの1/3~半分程度を目安に注ぐことが推奨されています。また後述しますが、ワインを注いだ後はグラスを傾けて回転させることで酸化を促進し香りをより楽しむことができます。グラスの中の変化もまた、ワインを楽しむ醍醐味のひとつです。
提供温度に気を付ける
提供する温度も気を付けてください。適切な温度で提供することで、風味が損なわれずに楽しむことができます。ワインの温度が高すぎると甘味と酸味のバランスが崩れて全体的にボヤけた印象になってしまったり、低すぎると渋みや酸味が強調されたり風味が閉じてしまいます。
一般的なガイドラインとしては白ワインは10〜12度、赤ワインはに14〜18度くらいが適切とされています。適切な温度で提供することで、ワインの酸味やタンニン、フルーティな香りがバランスよく感じられます。
見た目
ワインの外観(見た目)は、特徴やワインのスタイル(タイプ)を理解するうえで役に立ちます。さらには品質や熟成度についても推察可能となります。ただし、見た目だけでなく香りや味わいとの総合的な評価が必要です。
- 色: ワインの色はその年代や品種、熟成度などを推測するのに役立ちます。赤ワインの色は濃淡や透明度が異なり、年月を経るほど色が淡く、薄く変化します。グラスを少し傾けて、液面のエッジを見てみると若い赤ワインは紫色が強く、徐々にオレンジ色に変化します。白ワインではエッジが緑の色調なものは若く、徐々に黄色に変わっていきます。
- 濃度: ワインの濃度は、特定のブドウ品種や果実の濃さや濃縮度を表しています。深く濃い色のワインは、通常果実の濃厚な風味や力強い特徴を持っています。また発酵や熟成の過程で酸素に触れる環境(樽など)によっても変化することがあります。また、育成の環境を考えるうえで生産国や温暖か、冷涼かヒントにつながります。
- 光沢: ワインの光沢は、品質や状態を示す指標です。良質なワインは光沢があり、透明で輝きがあります。濁っているからと言って状態が悪いとは限りません。瓶に詰めるまでの間に、ワインをあえて濾さない生産者もいます。
- 泡立ち: スパークリングワインやシャンパンなどの泡立ちは、ワインの品質や二次発酵の程度を示す重要な要素です。泡が細かく長く続くものほど高品質なものとされます。
- レッグ(涙): レッグは、ワインがグラスの内側に付着して作る涙のような模様です。ワインのアルコールや糖分の濃度を示す指標であり、レッグが濃くてゆっくりと流れるほど、ワインの構造や甘みが豊かであることを示します。
香り
グラスから立ち上がる香りには様々な種類があります。その由来を考えることで、ブドウ品種や育った環境、醸造や熟成の過程などストーリーが詰まっています。
- 香りの由来: ワインの香りは果実由来の第1アロマ、醸造・発酵由来の第2アロマ、熟成由来の第3アロマ(ブーケ)の3つに分類されます。それぞれのアロマにはさまざまな香りのタイプが存在し、ワインの魅力に寄与しています。
- ワインの香りのタイプ: ワインの香りは多岐にわたり、フルーティ、花の香り、スパイシー、ハーブ、ミネラル、ウッディーなどの様々な要素を含んでいます。ワインの品種や産地、生産方法によって香りの特徴が異なるため、個々のワインを評価する際にはその香りのタイプに注目することが重要です。
- 香りの特徴: ワインの香りはそれがシンプルか複雑さを兼ね備えたものか個性を表現しています。香りは味覚を刺激し、ワインの風味やキャラクターを引き立てます。例えば、果実の香りが強いワインはフレッシュで爽やかな印象を与え、スパイシーな香りを持つワインは奥行きと興味深さを感じさせます。
- 香りの表現方法: 香りの解説は個人の感性や経験によって異なるため、一定の基準はありません。一般的には、果実の種類や特徴、花の香りやハーブのニュアンス、スパイスの香り、木の香りなど、具体的な言葉で香りを表現することが好まれます。また、香りの強さや複雑さ、バランスも評価のポイントとなります。こうしたワインの香りを表現する語彙は、共通した表現方法が好まれます。独創的なワインの表現をする場合もありますが、一般的には特徴を伝えるのにルールが存在します。
味わい
ワインの味わいの要素とバランスについて理解しましょう。酸味、甘み、苦み、ボディ感などが調和したバランスの良いワインは、品質や楽しみの幅を広げる要素となります。
- 味覚の要素: ワインの味わいは主に酸味、甘み、苦み、アルコールのボリュームなどの要素から成り立っています。これらの要素が組み合わさり、ワインの個性や特徴を形成しています。
- バランスの重要性: ワインの味わいにおいてバランスは非常に重要です。バランスが取れたワインは各要素が調和し、一つの要素が他の要素を圧倒することなく、統一感のある味わいを提供します。
- 酸味: 酸味はワインの新鮮さや活気を表現し、口中をスッキリとさせる役割を果たします。適度な酸味があり、他の要素とのバランスが取れているワインは高い品質を示します。酸味の少ないワインは、ぼやけた印象になります。料理と合わせる場合、少しだけ酸味が勝つくらいが最適といわれています。
- 甘み: 甘みはブドウ果実自体の甘さや補糖によって生まれます。ワインの甘みには果実の豊かさやコクを表現し、味わいに深みと魅力を与えます。適度な甘みがあるワインは飲みやすくなります。ワインにおいて酸味と甘みは逆相関の関係です。これらのバランスを感じることが味わいのポイントのひとつです。
- 苦み: 苦みはブドウの種や皮、茎などよってもたらされます。適度な苦みがあるワインは長期熟成に向いている場合があります。ただし、過剰な苦みはバランスを損なう可能性があるため注意が必要です。渋みの強いワインは、油の多い料理との相性がよく、口の中をさっぱりさせてくれる効果があります。
- ボディ感: ワインのボディ感はライト・ミディアム・フルボディなどの分類があります。ボディは口当たりや舌触りに影響を与え、ワインの重厚さや力強さを表現します。バランスの取れたワインとは、そのボディ感が他の要素(酸味、甘味、苦み、アルコール感)と調和しています。
余韻
ワインの余韻には「格」が出ます。こちらについて理解することで、ワインの品質や複雑さ、個性をより深く評価することができます。余韻の持続性やフィニッシュ、香りの複雑さと時間経過とともに起こる変化に注目してみましょう。
- 余韻とは: ワインを口に含んだ後、味わいや香りが舌や口の中に残る感覚を指します。余韻はワインの品質や複雑さを評価する上で重要な要素となります。
- 持続性: 余韻の持続性はワインの品質の一つの指標となります。品質の高いワインは余韻が長く続き、複数の層やニュアンスが感じられることがあります。数秒で終わるものもあれば、長いもので数十秒も続くワインが存在します。
- フィニッシュ: フィニッシュとは、ワインを飲んだ後に感じる最後の味わいを指します。余韻は味わいや香りがどのように消えていくかを表し、滑らかさやバランスの良さを示す要素です。甘味を残すものもあれば、滑らかでスッと消えるものもあります。
- 複雑さと変化: ワインの余韻は時間とともに変化することがあります。初めに感じた味や香りが徐々に変わり、新たな要素やニュアンスが現れることがあります。複雑なワインは余韻の中で様々な味わいや香りのレイヤーが展開され、飲み手を楽しませます。
- 余韻を味わう方法: ワインの余韻を十分に味わうためには、口の中でワインを少し動かし、舌などで味わいの要素を感じることがポイントです。ワインを飲み干したあとも、香りと味わいを同時に楽しみましょう。また、じっくりと時間をかけて味わうことが大切です。余韻の中で感じられるフルーツの余韻、スパイシーな余韻、タンニンの余韻などがワインの個性を感じてみてください。
スワリングして変化を楽しむ
スワリングは、グラスを手のひらで持ち、円を描くように軽く回転させることです。これにより、ワインが空気と触れ合い香りの放出を促進することができます。スワリングによって、ワインの香りがより広がり、複雑なアロマが感じられるようになります。また、スワリングによってワインの酸味やタンニンが柔らかくなり、口当たりがよくなる効果もあります。
- 方法: ワイングラスを持ち、軽くグラスを回転させます。スワリングの際には、グラスの底部をテーブルから少し浮かせることがポイントです。回転させる速度や角度は個人の好みによりますが、香りを引き立てるためには程よい強さで行うことが重要です。回す方向ですが、液面の回転方向に他人がいないことを確認してください。周りへの配慮もワインのマナーです。
- 効果: スワリングによってワイン中の香り成分が酸素に触れ、揮発性の高い化合物が放出されます。これにより、ワインの複雑な香りが広がり、香りのニュアンスや層がより明確に感じられるようになります。いわゆるワインが開いたというような状態を感じられるでしょう。
- テイスティング時への活用: スワリングはワインのテイスティング時に特に活用されます。スワリングを行いながら香りや味わいの特徴を評価し、ワインの品質やバランスを判断します。
おわりに
ワインをさらにおいしく飲むためのヒントをお話してきました。ワインに慣れてくると、それほど難しいことではありませんが最初はひとつひとつ確認しながら行うことでフォームもしっかり整い、自然とワインの世界に引き込まれていくことでしょう。
少しでも参考になれば幸いです。
テイスティングフォームをしっかり身に着けるには、独学では難しい部分があります。
スクールなどで体系的に学ぶことが最も最短だと考えられます。機会があれば、一度体験してみてください。

記事を書いた人

- ワイン愛好家に向けて2023年よりWebサイト「WINE自習室」でワインの魅力を発信。エレガントな赤、アロマティックな白ワインが好み、最近は陽気なイタリアワインがお気に入り、ワインを飲むのが楽しくなる情報をたくさん配信できるよう頑張ります。J.S.Aワインエキスパート2020年取得
最新の投稿
「WINE自習室」は、ワインに関する知識を深め、楽しんでいただくための情報をお届けするサイトです。
当サイトは、アフィリエイト広告収入により運営しております。記事を通じて、ワイン選びや知識を深めるお手伝いができれば幸いです。
なお、当サイト内のリンク先(楽天やYahooなど)で商品をご購入いただいた場合、運営者にアフィリエイト報酬が発生することがあります。
もし記事が参考になりましたら、ぜひバナー広告もご覧ください。皆さまのご支援が、今後のコンテンツ充実に繋がります。
これからも、ワインを楽しむひとときをサポートしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
コメントは受け付けていません。