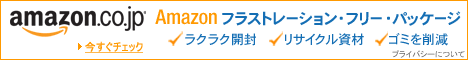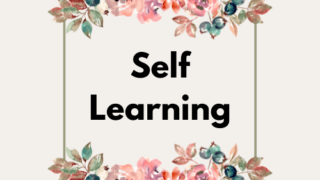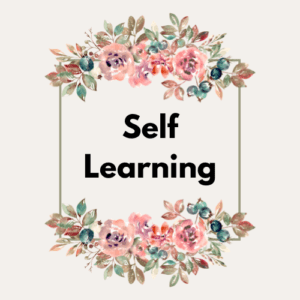ライト、エレガント、リッチ?ワインスタイルと味わいのヒント
ワインの味わいには、さまざまな要素が組み合わさっています。赤ワインと白ワイン、それぞれに特徴的なスタイルが存在し、その多様性が魅力です。本コラムでは、赤ワインと白ワインの味わいの要素を探ってみましょう。
赤ワインではライトなスタイル、エレガント系スタイル、そしてリッチ系スタイルがあります。一方、白ワインではニュートラル系スタイル、アロマティック系スタイル、そしてリッチ系スタイルが特徴的です。それぞれのスタイルには、品種の選択や生産地の気候条件などが大きく関与しています。
さあ、ワインの多彩な世界に浸りながら、その魅力を探求してみましょう。

赤ワインの味わい
赤ワインの味わいは、さまざまな要素が組み合わさっています。その中でも重要な要素を以下にまとめてみました。大きく3つで考えると良いと思います。簡単にアルコール度で判断できます。
- ライトなスタイル: 赤ワインの中でも軽やかなスタイルのものは、フレッシュな果実味や軽いボディを特徴としています。さわやかで飲みやすく、食前酒や軽い料理との相性が良いです。ブドウ品種では、ガメイやマスカット・ベーリーAが代表的です。価格帯にもよりますが、多くはフレッシュで軽快な赤ワインで、飲みやすさが魅力です。アルコール度数は12.5%~13%以下が多いです。
- エレガント系スタイル: エレガントなスタイルの赤ワインは、洗練された味わいや上品な酸味を持ちます。フルーティさと繊細さが調和しており、上質な料理や特別な場での楽しみにぴったりです。例えば、ピノ・ノワールやメルローなどが該当します。私、個人ではサンジョヴェーゼが好みです。アルコール度数は、12.5~14.0%程度だと思います。
- リッチ系スタイル: リッチなスタイルの赤ワインは、濃厚な果実味や豊かなボディが特徴です。濃密でコクのある味わいであり、ゆっくりと楽しむことができます。ステーキや濃い味付けの料理に合わせるのがおすすめです。例えば、カベルネ・ソーヴィニヨンやシラーなどが典型的なリッチ系の赤ワインになります。アルコール度数は、13.5~15.5%くらいまで幅広いです。
白ワインの味わい
白ワインも赤ワイン同様、さまざまな味わいの要素が存在します。以下に代表的な要素をまとめました。こちらも3つのタイプで覚えてしまいましょう。白ワインのスタイルは、香りの強さなどから分けても良いかもしれません。
- ニュートラル系スタイル: ニュートラルなスタイルの白ワインは、控えめな果実味と軽いボディが特徴です。爽やかでさっぱりとした味わいであり、シーフードや軽い料理との相性が良いです。例えば、樽熟成していないシャルドネや甲州、ミュスカデなどが代表的な品種です。
- アロマティック系スタイル: アロマティックなスタイルの白ワインは、芳醇な香りとフルーティな味わいが特徴です。複雑なアロマと個性的な風味を楽しむことができます。スパイシーな料理やエスニック料理に合わせると相性が良いでしょう。ゲヴュルツトラミネールやリースリング、ソーヴィニョン・ブラン、トロンテスなどが分かりやすいでしょう。
- リッチ系スタイル: リッチなスタイルの白ワインは、濃厚な果実味や豊かなボディが特徴です。しっかりとしたアルコール度数からくるボディでクリーミーな口当たりがあり、贅沢な味わいを楽しむことができます。是非リッチなバターを使った料理や濃いクリームソースの料理との相性が良いでしょう。しっかり樽が効いたシャルドネやヴィオニエなどの品種がこのスタイルでよく見られます。
各スタイルに影響するもの
ワインのスタイルは、ブドウ品種や生産地の気候、土壌、生産者の考え方など様々な要素が影響を与えています。
例えば、赤ワインのエレガントなスタイルは、ピノ・ノワールが栽培される冷涼な気候地域で生産されることが多く、その風味や酸味のバランスが優れています。逆にパワフルでリッチなスタイルは温暖な気候で育つブドウ品種から作られます。
また、白ワインのアロマティックなスタイルは、ゲヴュルツトラミネールやリースリング、ソーヴィニョン・ブランが多く見られる地域(フランスのアルザス、ドイツのモーゼル、オーストリアのヴァッハウなど)で栽培されます。
これらの品種は、ソーヴィニョン・ブラン(多様な気候で適応)を除いて冷涼な産地でよく栽培されます。これらは、鮮やかな酸味や芳醇なアロマが特徴であり、冷涼な気候や土壌条件で最良の成熟を迎える傾向があります。
冷涼な産地では、日照時間が比較的短く、気温の上昇が制限されるため、ワインの酸味がしっかりと保たれます。また、夜間の寒冷な気温が果実に緊張感を与え、ワインに複雑な味わいをもたらす要因となります。
ワインのスタイルを決定する要素の一つとして、土壌の特性も重要です。土壌の成分や排水状態は、ぶどうの根の成長や栄養摂取に影響を与えます。例えば、石灰質の土壌は、ワインにミネラル感や骨格を与える傾向があります。
ただし、産地の気候だけでなく、土壌条件や栽培技術、ワイン生産者の手腕などもワインの味わいに影響を与えます。したがって、必ずしも品種と産地の関係が一概には言えない場合もあります。
この辺りは、慣れてきたらブドウ品種や産地について、地理的な要素、気候条件、栽培方法、醸造の情報などがラベルに書かれていることもあり参考にすることで、より正確な知識を得ることが出来ます。
したがって、ワインの味わいを理解するためには、複数の要素を総合的に考慮する必要があります。
最後に
ワインの味わいは個人の好みによっても異なるため、自分の好みに合ったスタイルを見つけることも大切です。楽しみながら様々なワインを試してみて、自分に合った味わいを見つけてみてください。
ワインの世界は広大で奥深いものです。常に新しいワインや生産地が登場しており、探究心を持って楽しむことができますね。
記事を書いた人

- ワイン愛好家に向けて2023年よりWebサイト「WINE自習室」でワインの魅力を発信。エレガントな赤、アロマティックな白ワインが好み、最近は陽気なイタリアワインがお気に入り、ワインを飲むのが楽しくなる情報をたくさん配信できるよう頑張ります。J.S.Aワインエキスパート2020年取得
最新の投稿
「WINE自習室」は、ワインに関する知識を深め、楽しんでいただくための情報をお届けするサイトです。
当サイトは、アフィリエイト広告収入により運営しております。記事を通じて、ワイン選びや知識を深めるお手伝いができれば幸いです。
なお、当サイト内のリンク先(楽天やYahooなど)で商品をご購入いただいた場合、運営者にアフィリエイト報酬が発生することがあります。
もし記事が参考になりましたら、ぜひバナー広告もご覧ください。皆さまのご支援が、今後のコンテンツ充実に繋がります。
これからも、ワインを楽しむひとときをサポートしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。